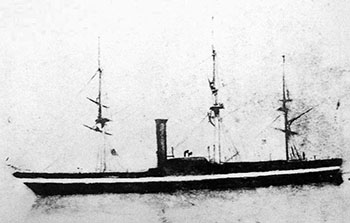NHK大河ドラマ「花燃ゆ」でも中心人物としてとりあげられている吉田松陰(寅次郎)。
脱藩や黒船での密航を企てるなど、たびたび騒ぎを起こしていた松蔭でしたが、ついに30歳の時に処刑されてしまいます。この記事では松蔭が処刑に際し残した「辞世の句」についてまとめます。
「日米修好通商条約」が松蔭処刑の発端
安政5年(1858年)のこと。井伊直弼が大老になると、江戸幕府は天皇の許しを得ず日本を代表する政府として「日米修好通商条約」を締結します。これは米側に領事裁判権を認め日本側に関税自主権がないなど、日本側に不利な条約だとされます。
松蔭はこの条約締結に対し「日本の安全が脅かされる」と激怒し、老中・間部詮勝の暗殺計画を企てます。この計画は久坂玄瑞、高杉晋作らに反対され実行されませんでしたが、松蔭の一連の倒幕への動き、幕府批判を長州藩は問題視し、松蔭は再び「野山嶽」に投獄されてしまいます。
安政6年には松蔭は江戸に送られ、幕府から尋問を受けます。ここで松蔭は心を尽くせば真意は伝わると考え、暗殺計画のことなど自分の考えを正直に話してしまうのですが、これが仇となり、死刑が決定してしまうのです。
辞世の句 込められた意味とは
死刑に処されることを悟った松蔭は、以下のような辞世の句を残しています。
親思う心にまさる親心 けふのおとずれ何ときくらん
意訳:子が親を思う以上に、親が子を思う気持ちは強いものだ。今日のこの報せを聞いた親は、なんと思うだろうか。
こちらの句は、家族に向けて詠われた句です。勉強家で勤勉な父・杉百合之助と前向きで明るい母・滝のことを想えば、感謝の念とともに、子が先に逝くことの申し訳なさを感じていたことでしょう。そして、もうひとつの句が以下のようなもの。
身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも 留め置かまし大和魂
意訳:もしこの命が武蔵(江戸を含む当時の武蔵国)の野辺で果てようとも、自身が貫いた思想や熱情は永遠に留めておきたいものだ
こちらは残される松蔭の弟子たちに向けて詠んだとされます。松蔭はこれまで自身が信じてきた考えが何一つ間違っておらず、死して後悔は無いという気持ちがあったのでしょう。自身の運命を受け入れるとともに、残された弟子たちに遺志を継いで欲しい、そんな想いを持っていたことが読み取れます。
関連記事
・【花燃ゆ】吉田松蔭・金子重輔が投獄される「野山嶽」「岩倉嶽」とは?
・【花燃ゆ】吉田松陰(寅次郎)が黒船で密航を企てた理由とは?