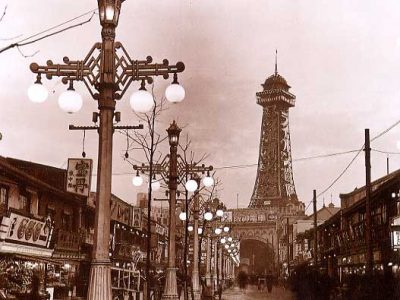NHK連続テレビ小説「わろてんか」に出演している本物の芸人、コメディアン、演芸関係者などをまとめます。
「わろてんか」は大阪の笑い、演芸界がテーマであり、本物のお笑い芸人、コメディアンなどが多数出演することが予想されます。この記事は、ドラマの進展にあわせて随時記事の追記、修正を行なっていきます。
なお、劇中に「架空のキャラクター」として登場している芸人、落語家たち(登場人物)については 「わろてんか」登場人物 芸人、落語家まとめの記事にまとめています。
「わろてんか」に出演している芸人たち
藤井隆…芸人・万丈目吉蔵役
まったく面白くない芸人・万丈目吉蔵。まったく仕事がないため、妻・歌子が経営している一膳飯屋で日がなブラブラし、夫婦喧嘩が絶えない。この夫婦喧嘩の面白さにより、後に「夫婦漫才」のパイオニアに…?
藤井隆(45歳)は、「よしもとクリエイティブ ・エージェンシー」に所属するお笑い芸人。「HOT!HOT!」のギャグやオカマキャラなどで人気を博し、歌手としても紅白歌合戦出場の経歴を持つ。
兵動大樹…太夫元・寺ギン役
芸人を寄席に派遣する「太夫元」で、大阪興行界の風雲児。「オチャラケ派」を結成して芸人を集結させ、大阪のお笑いの世界に旋風を起こす。
兵動大樹(47歳)は、「よしもとクリエイティブ ・エージェンシー」に所属。お笑いコンビ「矢野・兵動」のボケ担当。「バラエティー生活笑百科」などの出演で知られる。
・【わろてんか】寺ギンのモデル人物は「黒政」こと岡田政太郎 吉本創業時に深く関わる
内場勝則…元席主・亀井庄助役
経営不振により廃業した寄席の元席主。ヒロイン夫婦が寄席を売って欲しいと頼み込むが、亀井はまったく相手にしない。
内場勝則(57歳)は、「よしもとクリエイティブ ・エージェンシー」所属のお笑い芸人、喜劇俳優。「吉本新喜劇」の座長を務めるなど、「喜劇俳優」としての活動で知られる。
前田旺志郎…芸人・キース(幼少期)役
藤吉がもぐり込む旅一座で育った芸人。頭の回転が早く博識、インテリだが、たびたびトラブルを巻き起こす天然ぶりも見せる。後に「しゃべくり漫才」のパイオニアになっていく。
前田旺志郎(16歳)は、「松竹エンタテインメント」所属のお笑い芸人、俳優。元子役で、2007年頃から実兄・前田航基とともにお笑いコンビ「まえだまえだ」を結成。映画「奇跡」(2011年)の演技が高い評価を受けるなど、俳優としても活躍している。
桂南光…落語家役
第1回放送ほかで登場。京都で行なわれていた「福楽座」の公演に出演していた、大阪からやってきた落語家役。桂南光本人が得意とするネタ「ちりとてちん」を演じていたが、てんが高座に乱入し、怒って帰ってしまう。
桂南光は上方噺家で、タレントとしての活動でも知られる。
豊来家玉之助…皿回し芸人役
第1回放送で登場。京都の神社の祭りの日に行なわれていた福楽座の公演で、皿回しを行なう芸人として登場。観客をわかせる。
豊来家玉之助は、傘回しや皿回しを行なう太神楽曲芸を行なう芸人。
時代屋武…南京玉すだれ芸人役
第1回放送で登場。薬まつりが行なわれていた神社の境内で、黒ぶち丸眼鏡のおじさんが伝統芸能・南京玉すだれを披露。
時代屋武は、丸眼鏡がトレードマークの大道芸人。
露の団四郎、露の団六…俄芸人役
第6回放送で登場。てんがもぐり込んだ薬まつりの福楽座の公演で、「俄(にわか、仁輪加)」芸を披露。俄は、歌舞伎の一場面を面白おかしく演じた芸。「この恨み、はらしてくれよー」とやっている時に猪に扮した藤吉が間違って乱入し、舞台が台無しに。
露の団四郎、露の団六はともに落語家。仁輪加(にわか)師として、一門で「軽口にわか」の伝統芸を守り伝えている。
海原はるか・かなた…八卦(占い師)役
10月16日(月)、第13回放送に占い師役として二人揃って登場。はるかはお馴染みの髪の毛芸も披露。
てんと「運命の再会」を果たした藤吉は、リリコに言わるまま八卦を行なう占い師(かなた)に見てもらうことに。かなたはリリコから裏金をもらっており、てんとの再会は災いの元だとウソの占い結果を伝える。
一方、そこに偶然通りかかったてんは、かなたの横にいたはるかにお見合い相手の相を見てもらうが、他に好きな人がいることを見破られてしまう。それを藤吉が横で聞いてしまい…。
月亭八光…落語家(伝統派)役
11月15日(水)、第39回放送で登場。
風鳥亭に出てくれる落語家を探していた藤吉が出演を頼み込んだ伝統派の落語家として登場(役名なし)。藤吉はうな重で接待をするが、「大体やでえ、鰻特上やのうて並やがな!並の噺家に頼むんやったらな、オチャラケ派に行きなはれ」と怒らせてしまう。
笑福亭べ瓶…喜楽亭文鳥の弟子役
11月16日(木)、第40回放送で登場。伊能の紹介で伝統派の大看板・喜楽亭文鳥に会うことが出来た藤吉。その後ろで控えていたのが、文鳥の弟子たちでした。
笑福亭べ瓶(しょうふくてい・べべ)は、笑福亭鶴瓶の13番目、最後の弟子。
プリマ旦那(野村尚平、河野良祐)…暑がる寄席の客
11月20日(月)、第43回放送で登場。
亀井の提案により、寄席内に火鉢を置いて暑くすることで客の回転をあげようと試みた風鳥亭。プリマ旦那の二人が演じる男性客は暑さに耐えられず、怒って帰ってしまう。
プリマ旦那はともに大阪出身の野村尚平、河野良祐によるお笑いコンビで、よしもとクリエイティブ・エージェンシーに所属。NHK大阪制作のネタバトル番組「谷4爆笑養成所」(2017年6月に近畿地方で放送)で優勝し、「わろてんか」の出演権を獲得していた。
笑福亭銀瓶…冷し飴を飲みたがった落語家(松葉亭ぽん蝶)
11月21日(火)、第44回放送に登場。
風鳥亭に出演していた落語家(笑福亭銀瓶)が暑さのあまりに飲料「冷し飴」を買ってくるように頼んだことから、てんは冷し飴を寄席でも販売してみることを思いつく。※この落語家は23日(木)の放送で落語を披露し、松葉亭ぽん蝶の名であることが判明。
笑福亭銀瓶(しょうふくてい・ぎんぺい)は兵庫県神戸市出身の落語家で、笑福亭鶴瓶の弟子。師匠同様、落語家だけでなくタレントとしても活動するなどマルチな才能を持つ。
華井二等兵…寺ギンからクビを宣告される芸人「梅王」
11月29日(水)、第51回に登場。
寺ギンから芸人として見込みがないから早く故郷へ帰れと言われてしまい、頭を下げて去る芸人役。
華井二等兵は松竹芸能所属のピン芸人で、薄髪が特徴的。華井二等兵のTwitterによれば、この芸人の設定上の芸名は「梅王」だとか。
高本剛志(雷ジャクソン)…風太が見つけた子どもウケの良い芸人
12月1日(金)、第53回放送に登場。
寺ギンのもとで寄席の勉強を始めた風太が見つける、子どもウケの良い芸人コンビ「助九芳九」の片割れ(右側)として登場。
高本剛志は松竹芸能に所属する元海上自衛官芸人で、黒木俊彦とともにコンビ「雷ジャクソン」を組んでいる。
寄川展由(風穴あけるズ)…風太が見つけた子どもウケの良い芸人
12月1日(金)、第53回放送に登場。
寺ギンのもとで寄席の勉強を始めた風太が見つける、子どもウケの良い芸人コンビ「助九芳九」の片割れ(左側)として登場。
寄川展由は松竹芸能に所属する芸人で、風穴あけるズというトリオのコンビを組んでいる。
佐藤太一郎…警官役
12月4日(月)、第55回放送に登場。アサリを賽銭泥棒と勘違いし、追い回す警官役。芸人たちのことを良く思っていない様子。
佐藤太一郎は、吉本新喜劇で活躍するお笑い芸人。大阪市出身、39歳。
春風亭柳朝…東京の落語家(目黒亭柳三)役
1月13日放送、第85回放送に登場。
関東大震災復興支援の興行で風鳥亭の高座にあがった東京の落語家・目黒亭柳三役。大阪の観客の前で「寿限無」を披露し、笑いをとる。
桂文枝…柳々亭燕團治役
1月30日放送、第99回放送から登場。日本一の寄席チェーンとなった北村笑店に所属する、大物の師匠役。新しい時代のスター芸人発掘を考えるてんを後押しする…?
燕團治の弟子役として桂三語、桂三実も登場。
旭堂南陵…北極先生役
2月6日、第105回放送に登場。北村笑店に所属する講談師。風太のもとで修行中の隼也がお茶を出すと、熱すぎることに怒る。また、隼也に金を渡して「飴ちゃん」を買ってくるように頼む。
旭堂南陵は上方の講談師。朝ドラ「あさが来た」では、加野屋と懇意の商人仲間「祇園屋」として登場している。
玉田玉秀斎…若丸師匠役
2月6日、第105回放送に登場。風太のもとで丁稚修行中の隼也に、うどんの出前を頼む。
玉田玉秀斎は、大阪生まれの講談師。大阪市立大を卒業し、8カ国語を操るインテリでもある。師匠でもある旭堂南陵も「北極先生」役で同時出演。
ラフ次元(梅村賢太郎、空道太郎)…芸人・右貞、左貞
2月28日、第124回放送に登場。
東京の「新世紀芸能」から芸人の引き抜き攻勢を受けている北村笑店。亀井は所属芸人が引き抜き工作を受けていないかチェックする役割を任され、若手芸人コンビ「右貞左貞」にいい移籍話があるとカマをかけるが、「右貞左貞」は北村に恩義があるとこれを断る。
よしもとクリエイティブ・エイジェンシー所属のコンビ「ラフ次元」(梅村賢太郎、空道太郎)は、昨年11月に行われた「わろてんか」出演をかけたオーディションで優勝し、ドラマ出演権を獲得していた。
西川きよし…農家の主人・治平役
最終週に登場予定。
戦時下でてんたちが疎開することになる滋賀の農家の主人・治平役。孫を戦争に出しており心から笑うことが出来なくなった治平は、てんたちと交流するうちに次第に笑顔を取り戻すことに。